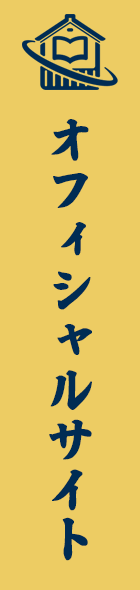丸背(まるぜ)とは?
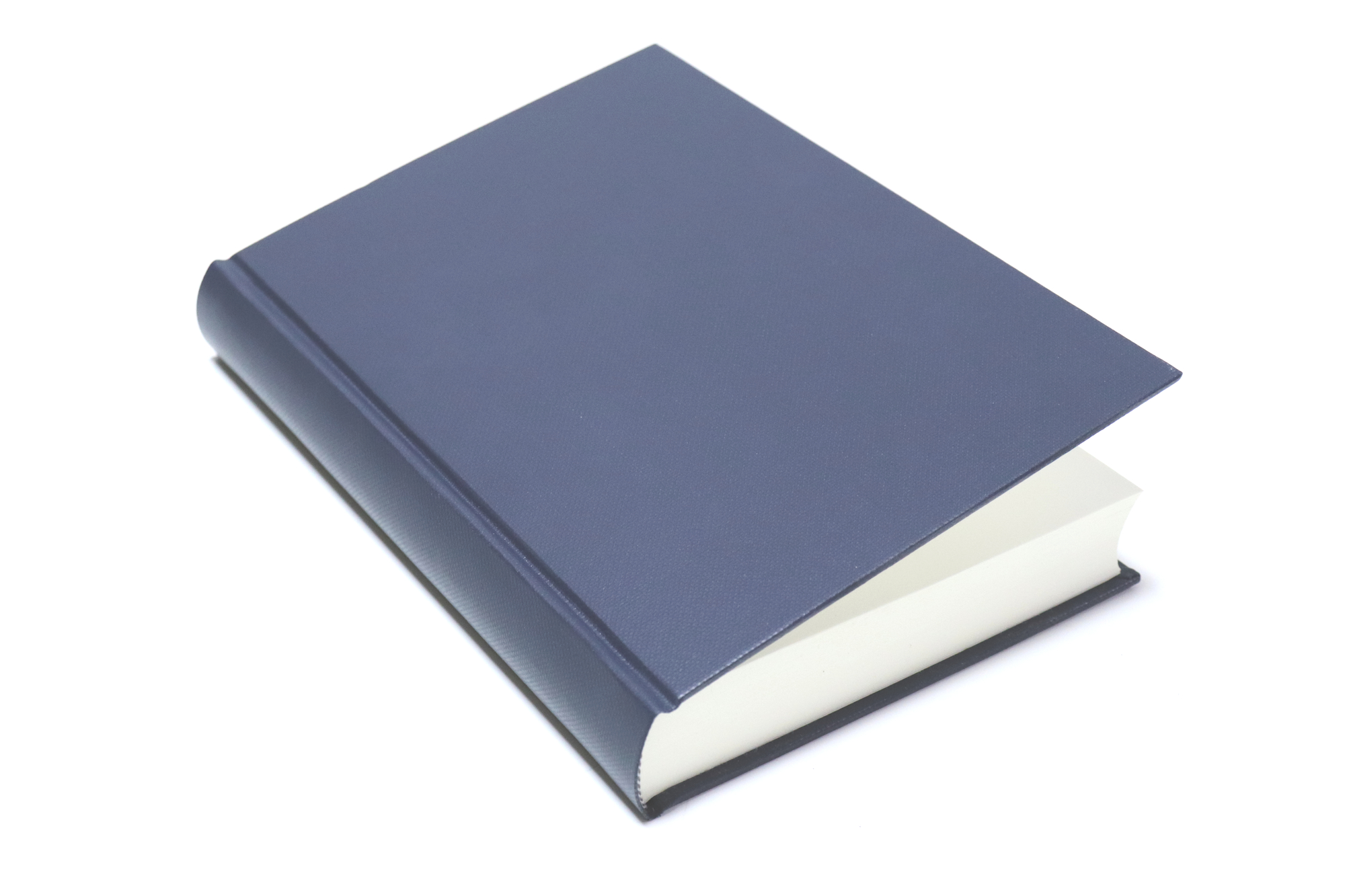
「丸背(まるぜ)」とは、上製本の背表紙部分に丸みのある製本方法です。
丸背は、本の開きが良いことから、ページ数が多い本におすすめです。
また、本を開いた際に外側になる部分である小口(こぐち)にも丸みがつくため、ページがめくりやすくなるのが特徴です。
今回は、角背(かくぜ)との違いについてもご紹介します。
丸背とは?
そもそも上製本の背には丸背と角背とがあります。
丸背とは、上製本の背表紙に凸の丸みができる製本方法です。本の開きが良いことから、厚みのある本に向いています。また、本を開いた際に外側になる小口にも丸みがついています。つまり、背表紙側が凸の丸みであるのに対し、小口側は凹の丸みになります。このように、小口にも丸みがつくことによって、ページがめくりやすくなります。
丸背は、見た目が美しく高級感のある印象になります。手作業でおこなう工程も多く、作りが複雑なため職人には高い技術が求められます。製作時間も長くかかるため、価格は角背よりも高くなるのが一般的です。
丸背で製本する理由とは?
上製本の背表紙を丸背にする理由は、以下の通りです。
・本の型崩れを防止するため
・本の開きを良くするため
・中身が小口側にせり出してしまう「逆バッケ」を防止するため
角背とは?

角背とは、上製本の背表紙部分が平らな製本方法です。背が平らで厚みが少ない冊子の製本に向いています。背が平らなので、本棚にしまったとき見た目がスッキリ、カッチリしており重厚で高級な印象を与えます。
角背は丸背とは異なり、作りがシンプルな分、比較的低コストで作ることが可能です。
おおよその目安としまして、厚さ2cm程度でしたら角背がおすすめです。それ以上になると丸背が推奨されています。というのも、ページ数が少ないものを丸背で製本しようとしても、背表紙の横幅が狭いとしっかりとした丸みを出すことができません。また逆にページ数が多い場合は、角背で製本してしまうと読んでいるうちに背が割れてしまうケースもあります。
まとめ
今回は、丸背についてご紹介してきましたがいかがでしょうか。
上製本の背には、丸背と角背とがあります。
丸背は、本の開きが良いことから厚みのある本に向いています。また、小口側にも丸みがつくことでページが開きやすいというメリットがありました。
ただし、手作業でおこなう工程も多いため、製作時間が角背よりもかかってしまううえ、費用も高くなります。
また、角背は上製本の背表紙部分が平らになる製本方法です。厚みが少ない冊子向きで、本棚にしまった際に見た目がスッキリするのが特徴です。
その一方で、丸背よりもコストを抑えることはできるものの、読んでいるうちに背が割れてしまうというデメリットもあります。
本を作りたいと考えている方は、こうした点を踏まえて丸背にするか角背にするかを決めると良いでしょう。
大倉印刷は、2024年には文京区で創業40年となりました。
培った実績と経験で、短納期案件や少部数から多部数をこなしてきた豊富な実績がございます。
お客様の様々なニーズに応えるワンストップ生産体制にて、印刷、製本加工、納品・発送までの一貫生産
都内有数印刷機器の保有数です。
文京区に自社および自社工場を持つ利便性の良さをお客様のご要望に最大限活用させていただきたいと思っております。
大倉印刷だからこそ、できる形をご案内させていただきます。
丸背はもちろん、その他印刷用語辞典に記載されてる内容、載っていないものでも、まだまだ更新中の用語辞典ですので、どんなことでもあらゆるご質問やご不明点に誠心誠意対応させていただきます。
お気軽にご相談お問い合わせください。
#丸背 #上製本丸背角背 #角背 #丸背メリット #角背特徴 #大倉印刷 #印刷 #製本加工 #文京区印刷製本 #印刷会社 #製本会社 #用語集
大倉印刷では印刷、製本のお困り事に真摯に対応させて頂きます。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
Copyright © 大倉印刷株式会社 All Rights Reserved.