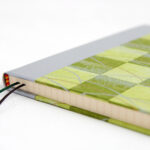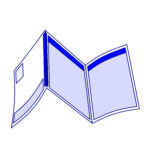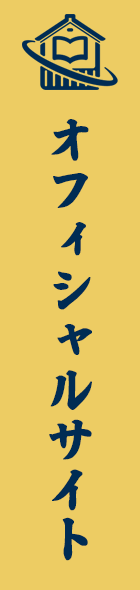奥付(おくづけ)とは?
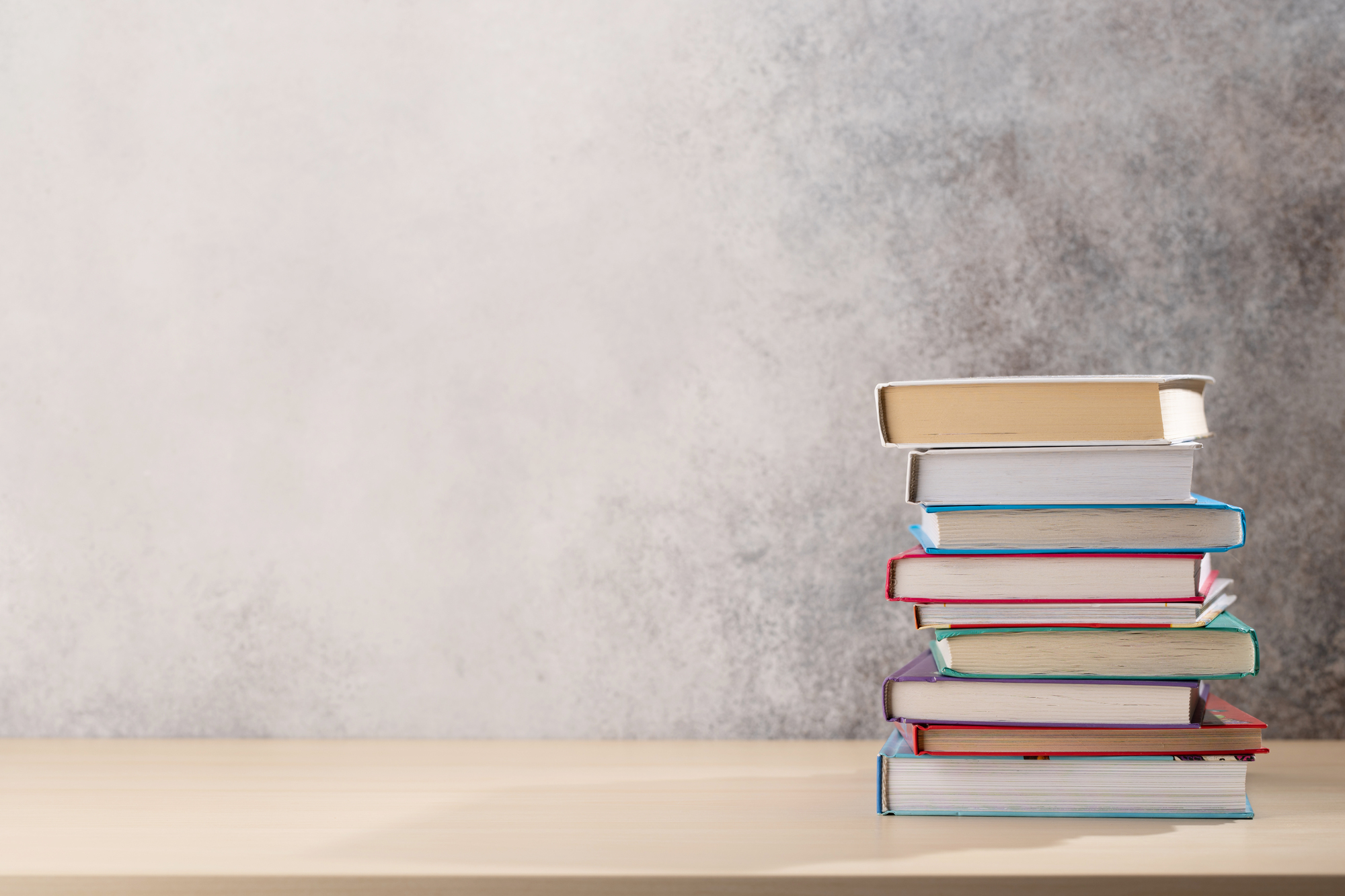
「奥付(おくづけ)」とは、同人誌の巻末に記載されている、タイトル、著者名、発行日、発行者、発行所、印刷所などの書誌情報のことです。
奥付は、出版物に関する責任の所在を明確にするために必要な部分となります。法的義務は取り払われたものの、書店流通のためには事実上必要とされています。
また、乱丁や落丁などの不備があった際に、読者が問い合わせする際の連絡先としての機能も持っています。
今回は、奥付の意味やどうのような情報を記載する必要があるのかなどについて詳しく解説していきます。
奥付とは?
奥付とは、書籍の巻末に記載されているタイトル、著者名、発行日、発行者、発行所、印刷所などの書誌情報のことです。奥付は、同人誌を制作する際に必ず必要になるもので、奥付がない場合には印刷会社が印刷を受け付けてくれないケースもあります。
【奥付の役割】
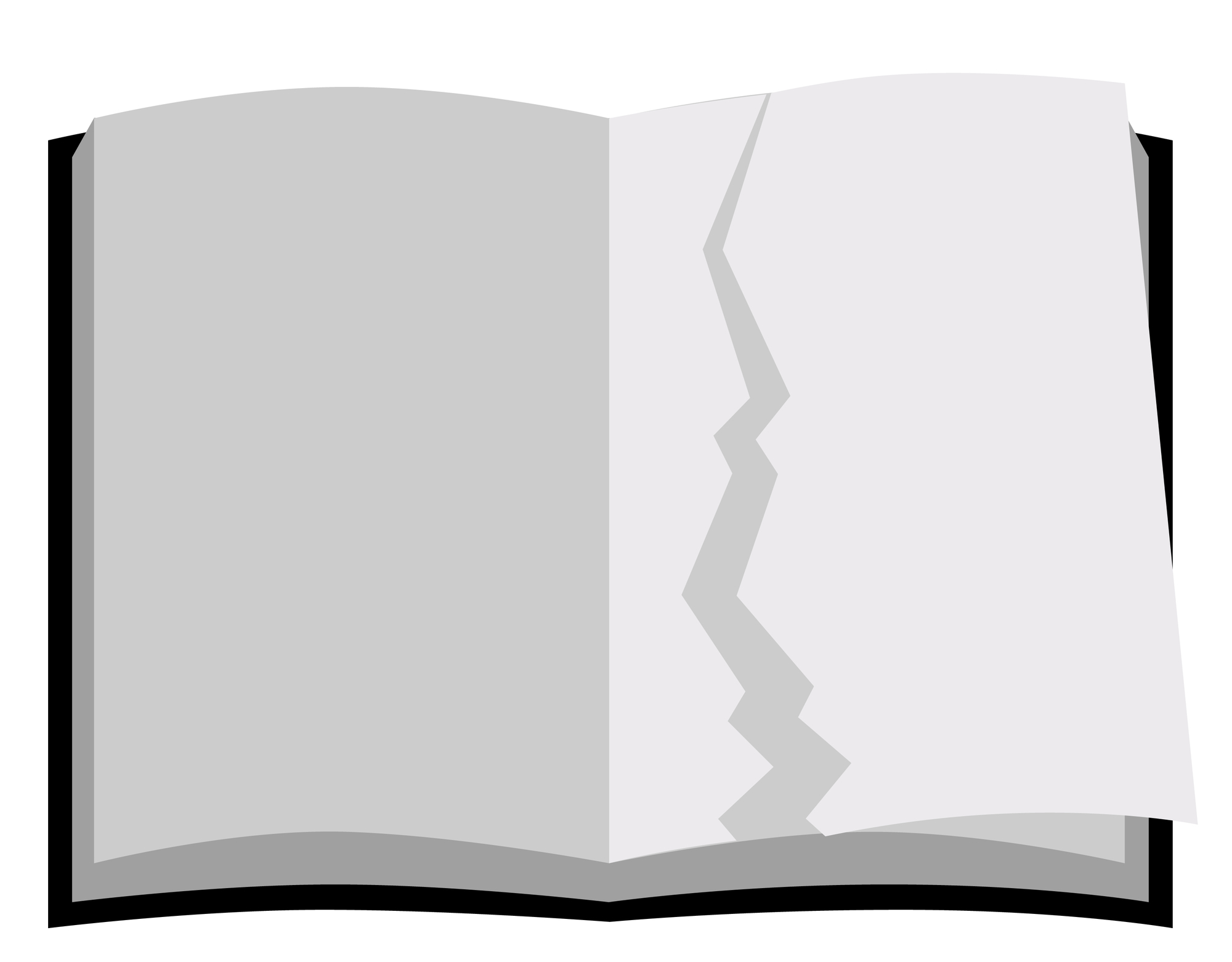
奥付は、出版物に関する責任の所在を明確にする役割を持っています。法的な義務は取り払われたものの、書店流通のためには事実上必須とされます。
また、乱丁や落丁などの不備が生じた場合に、読者が問い合わせをする際の連絡先としての役割も果たしています。
さらに、出版社や著者の情報が記載されていることによって、読者が出版物の正当性を判断する材料となります。
このほか、版数や刷数が多いほど、その書籍が多くの人々に読まれており人気があることの目安ともなります。
印刷会社サイドにとっても、制作に携わった企業として自社の実績をアピールする場ともなります。
奥付に記載する情報
奥付には決まったルールや形式はありません。また、縦書きでも横書きでもOKです。ただし、共通して記載する必要がある最低限の情報はあります。ここでは、奥付に含まれる主な情報をご紹介します。
〇書籍の正式名称
〇発行年月日
〇著者名
〇発行者、発行所(出版社名)
〇印刷所名
〇版数・刷数
〇ISBNコード(International Standard Book Number)
〇連絡先
【書籍の正式名称】
奥付には、制作する書籍の正式なタイトルを記載します。サブタイトルや英語表記、ボリュームやナンバーなどがある場合、これらの情報も一緒に記載します。
【発行年月日】
制作する書籍が印刷製本された年月日も奥付に記載します。一般的に発行年月日は、印刷製本から市場に流通するまでの期間を考慮するため、実際に印刷した日から2週間後くらいに設定されます。また、本の内容に修正や加筆があった場合は、初版発行日に加えて第二版発行日も記載します。
【著者名】
奥付には、その書籍を書いた著者の名前も記載します。著者名は、必ずしも個人名である必要はなく、ペンネームや団体名を記載してもOKです。
【発行者、発行所(出版社名)】
制作する書籍の発行責任者名を記載します。ほとんどの場合、出版社の代表取締役や編集部の担当者名が記載されます。また、その書籍を発行した企業や組織名も記載します。
【印刷所名】
その書籍を印刷、製本した会社名を記載します。
【版数・刷数】
その書籍が何回目に印刷されたものなのかを示しています。
ここで、版と刷は、それぞれ次のような意味を持っています。
・版……原版を表し、印刷のもととなるもの。
・刷……印刷した回数を表すもの。
つまり「初版 第3刷」となっている場合、修正されていない最初の版で、3回目に刷ったものという意味になります。
【ISBNコード(International Standard Book Number)】
ISBNコードは書籍を識別するための固有の番号のことです。世界中の書籍につけられており、奥付に加えて裏表紙にも記載することが規定されています。
【連絡先】
その書籍を編集した会社の問い合わせ先を記載します。住所や電話番号のほか昨今では、メールアドレスやウェブサイトのURL、ウェブサイトへ誘導するためのQRコードなどの記載も増えています。
奥付に記載しないほうが良い情報
奥付には記載すべきではない情報もあります。こちらも併せて覚えておくと良いでしょう。
【定価】
その書籍の定価は記載しないほうが良いでしょう。
なぜなら、将来的な価格改定や税金の変化にも対応できるようにするためです。書籍の多くが、カバーのみに定価を記載しているのは、こうした理由からです。
【個人情報】
奥付には、個人情報も記載すべきではありません。個人情報とは、著者の住所や電話番号、メールアドレス、SNSアカウントなどです。特に、自費出版の場合は、掲載しないように注意しましょう。
【検印】
奥付では、著作権者の検印は近年において省略されています。以前は、その書籍の著作権者を示すために用いられていましたが、手間がかかるといった観点から一般的に記載しない方向性になりました。ただし、検印の代わりに、「著作権者名(コピーライト)」を記載するケースもあります。
電子書籍における奥付
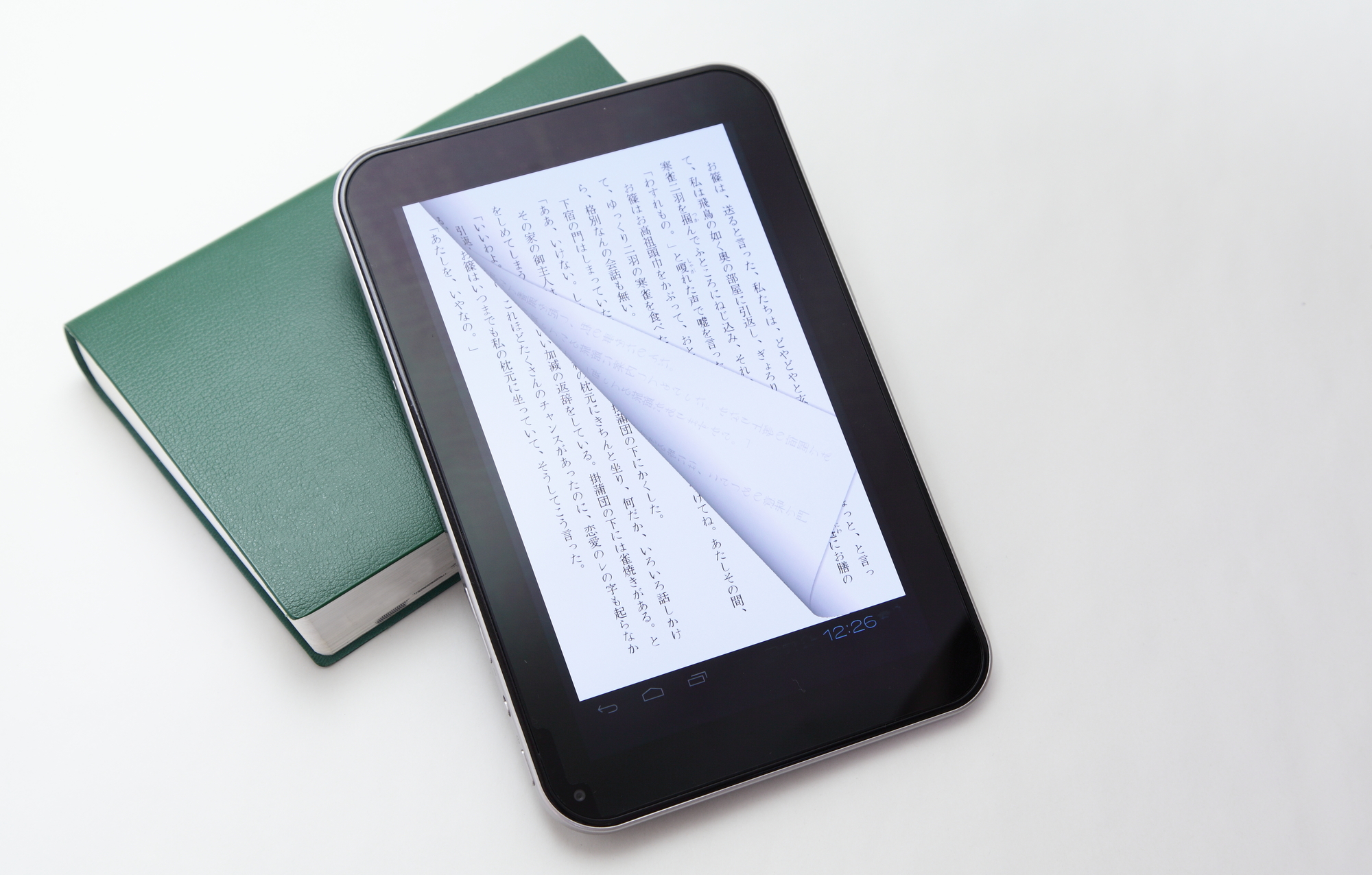
奥付は、昨今の電子書籍の流通量増加により、電子書籍においても基準作りが進められてきました。電子書籍「奥付」推奨モデルを検討している日本電子書籍出版社協会によると、以下の5項目が電子書籍における奥付必須項目とされています。
〇書名(書籍のタイトル)
〇著作者名
〇発行元(出版社名)
〇著作権者名(Copyright)
〇電子書籍発行日(制作日)
また、以下の3項目は記載が推奨されているものです。
〇電子出版コード(20桁)
〇底本情報(発行年月日や版数など)
〇複製/改ざん禁止条項
参照:日本電子書籍出版社協会 一般社団法人デジタル出版社連盟「電子書籍奥付推奨モデル」
まとめ
今回は、奥付についてご紹介しました。同人誌を制作する上で、奥付は非常に重要なものとなります。奥付は、紙の書籍も電子書籍においても、その“本の責任の所在”を示す大切なものですので、必ず記載するようにしましょう。
大倉印刷では、同人誌の印刷のご依頼も承っております。同人誌制作をお考えの方は、お気軽にご相談くださいませ。経験豊富なスタッフ一同、心を込めてご対応させていただきます。
大倉印刷は、2024年には文京区で創業40年となりました。
培った実績と経験で、短納期案件や少部数から多部数をこなしてきた豊富な実績がございます。
お客様の様々なニーズに応えるワンストップ生産体制にて、印刷、製本加工、納品・発送までの一貫生産都内有数印刷機器の保有数です。
文京区に自社および自社工場を持つ利便性の良さをお客様のご要望に最大限活用させていただきたいと思っております。
大倉印刷だからこそ、できる形をご案内させていただきます。
奥付はもちろん、その他印刷用語辞典に記載されてる内容、載っていないものでも、まだまだ更新中の用語辞典ですので、どんなことでもあらゆるご質問やご不明点に誠心誠意対応させていただきます。
お気軽にご相談お問い合わせください。
#奥付 #奥付とは #奥付記載理由 #奥付電子書籍 #大倉印刷 #印刷 #製本加工 #文京区印刷製本 #印刷会社 #製本会社 #用語集
大倉印刷では印刷、製本のお困り事に真摯に対応させて頂きます。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
Copyright © 大倉印刷株式会社 All Rights Reserved.