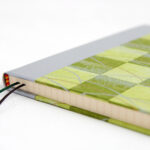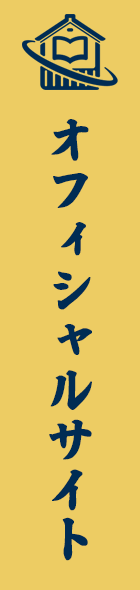色校正とは?

「色校正」とは、色をみて、元データと印刷物の仕上がりとで色味の違いや認識のズレがないかどうかを確認するために事前に試し刷りによって検証する作業のことです。
色校正は、印刷前に行われ、結果がイメージと異なる場合には補正が必要となります。このようにして、色の調整や統一性を守るのです。
色校正とは?
色校正とは、印刷における補正の一つです。印刷前に色をみて、元データと印刷物の仕上がりとで色味の違いや認識のズレがないかどうかを確認するために試し刷りの作業を行います。
そもそも印刷の補正には、大きく分けて「文字・デザイン補正」と「色校正」の2種類があります。「文字・デザイン補正」は、作成している紙面と原稿を照合して誤植やデザインの意図の相違がないかどうかをチェックする作業です。その一方で、色校正は、色に着目した補正です。色の調整や統一性を守るために、この工程で印刷の色の基準が決定されるのです。
色校正が必要な理由

色校正は、印刷物を作成するうえで必要不可欠な工程です。ここでは、色校正が必要な理由について解説します。
〇モニター画面の色と印刷物の色の違いを確認するため
〇印刷用紙によって色が変わるため
〇人によって色の認識が異なるため
〇色の違いによるトラブルを防ぐため
〇印刷物の擦り直しを防ぐため
【モニター画面の色と印刷物の色の違いを確認するため】
モニター画面で希望の色を選んだとしても、紙に印刷してみるとその色とは異なるケースもあります。それは、モニターと印刷物とでは色の表現方法が異なるからです。
パソコンのモニター画面では、「RGB」が一般的で「Red(赤)」「Green(緑)」「Blue(青)」の光の三原色を混ぜ合わせて色を再現しています。これは加法混色と呼ばれ、混ぜれば混ぜるほど白色に近づいていきます。
一方で、印刷物においては、「CMYK」が一般的です。CMYKとは、「Cyan(シアン)」「Magenta(マゼンタ)」「Yellow(イエロー)」の色材の三原色に「Key plate(キープレート)」を加えた色の表現方法で減法混色と呼ばれています。
このようにして、それぞれ色の表現方法が異なることから、RGBで表現可能であってもCMYKで出力できない色が存在し、パソコンで確認した色と印刷物の色が異なるケースが生じてしまうのです。
こうしたことを解決するために、出力結果を予測する色校正が必要になります。色校正によってモニター画面で見えていた色合いを印刷物でも忠実に再現することが可能となります。
【印刷用紙によって色が変わるため】
印刷用紙にはさまざまな種類があり、それぞれに紙質も異なるため、同じ色であっても、印刷した紙によって色の印象がガラッと変わります。
本来ならば、色の再現率が高い用紙を使用したいところですが、予算によっては再現率の低い用紙にせざるを得ないこともあります。このようなケースでは、出来上がりは全く違った色味になってしまうため、色校正で大きなズレがないかどうかを確認し、場合によっては、印刷用紙を変更することも考えられます。色校正を行うことで、印刷用紙によってどの程度の色の違いが出るのかを確認できます。色校正で確認し、紙質による色の違いが許容範囲内であるかどうか、それとも異なる種類の用紙に変更するかどうかの判断が可能となります。
【人によって色の認識が異なるため】
印刷物の色をどのように認識するかは、人それぞれ異なります。生活環境や感性、経験などの影響を受けて見る人によって、色に対する感覚が違うのです。しかしながら、特に広告やデザイン業界においては、正確な色の再現がブランドイメージや商品を宣伝するうえでは大変重要になります。そこで色校正を行うことで、顧客のニーズに合わせた色の再現が可能となり、満足度の高い印刷物を作成することが可能となります。
【色の違いによるトラブルを防ぐため】
昨今増えているのが、カタログに掲載されている商品と実物の色の違いによるトラブルです。カタログ上では、落ち着いた雰囲気の色味だったのに、届いた商品は派手な色であったなどのようなトラブルが多く、返品や交換による余計な業務が増えてしまいます。こうしたことを防ぐためにも、色校正で実物に近い色かどうかを事前に確認することが大切です。
【印刷物の擦り直しを防ぐため】
色校正をせずに印刷を進めてしまい、出来上がった印刷物がイメージと全く違うということもあります。この場合、再度刷り直しをしなければならず、プラスの費用が発生するだけでなく、納期も遅れることに…。事前に色校正をしておくことで、イメージ通りに仕上がるかどうかの確認もできるので、刷り直しを避けられるでしょう。
色校正をする際の注意ポイント

色校正をする際には、以下の点に気を付けましょう。
⚠光の加減によって色の見え方が変わる
⚠人物の顔色や血色は変化しやすい
⚠修正の際に具体的な指示をする
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
【⚠光の加減によって色の見え方が変わる】
色校正をする際には、照明の影響を加味する必要があります。というのも、光の加減や照明の種類によって印刷物の見え方が大きく変わるからです。なかでも、赤っぽい電球色や青っぽい昼光色のような光のもとでの確認はNGです。このような光は、特定の色を強調してしまう傾向にあり、正確な色の判断が難しくなってしまうでしょう。
したがって、色の再現性を確認するためには、太陽光に近い昼白色の照明で行うことをおすすめします。
【⚠人物の顔色や血色は変化しやすい】
色校正において、人物の顔色や血色は特に気を付けなければなりません。ポートレートや広告などにおいて、人物が主要な役割を果たす場合、その色の再現性が全体的な質を決めてしまうからです。色校正を誤り、青や緑が強調されてしまった場合、不健康な人の印象を与えてしまうことになります。しかしながら、ただただ血色が良く見えるだけでは不十分です。たとえば、ファッション系のブランドのイメージやコンセプトに合った色味の調整が必要となるケースもあるのです。つまり、規定色の正確さだけでなく、全体のバランスやコンセプトとの調和も考慮して色校正を行うことが重要です。
【⚠修正の際に具体的な指示をする】
色校正を行う場合、最も重要となるのが修正の際の具体的な指示です。抽象的な言葉で伝えても、印刷会社は何をどのように修正すれば良いか判断が付きません。その結果、品質に影響を及ぼしてしまいます。たとえば、「この青をもう少し明るくして欲しい」や「この部分のコントラストを強くして」など、修正したい箇所とその方向性を明確に伝えるようにしましょう。また、修正の程度も段階を定めて伝えることで、より精度の高い色校正が可能となります。
まとめ
色校正は、大切な印刷物をイメージ通りに仕上げるためには必要な工程です。そのため、最初に色校正を行う場合や、言葉での説明が難しい場合には、印刷会社としっかりと連絡を取り合い、具体的に指示を伝えることが大切です。同じ色だとしても、人によってイメージする色合いは異なります。人ぞれぞれの認識のギャップを埋めるためにも、しっかりと色校正を行うことをおすすめします。
大倉印刷は、2024年には文京区で創業40年となりました。
培った実績と経験で、短納期案件や少部数から多部数をこなしてきた豊富な実績がございます。
お客様の様々なニーズに応えるワンストップ生産体制にて、印刷、製本加工、納品・発送までの一貫生産
都内有数印刷機器の保有数です。
文京区に自社および自社工場を持つ利便性の良さをお客様のご要望に最大限活用させていただきたいと思っております。
大倉印刷だからこそ、できる形をご案内させていただきます。
色校正はもちろん、その他印刷用語辞典に記載されてる内容、載っていないものでも、まだまだ更新中の用語辞典ですので、どんなことでもあらゆるご質問やご不明点に誠心誠意対応させていただきます。
お気軽にご相談お問い合わせください。
#色校正 #RGB #CMYK #色校正注意点 #大倉印刷 #印刷 #製本加工 #文京区印刷製本 #印刷会社 #製本会社 #用語集
大倉印刷では印刷、製本のお困り事に真摯に対応させて頂きます。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
Copyright © 大倉印刷株式会社 All Rights Reserved.