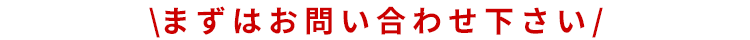右綴じと左綴じの使い分け方のルールをご存知でしょうか。
右綴じと左綴じの使い分け方は、本文が縦書きがメインなら「右綴じ」、本文が横書きがメインなら「左綴じ」が一般的です。
こうすることで、自然な流れで文字を読み進めることができるのです。
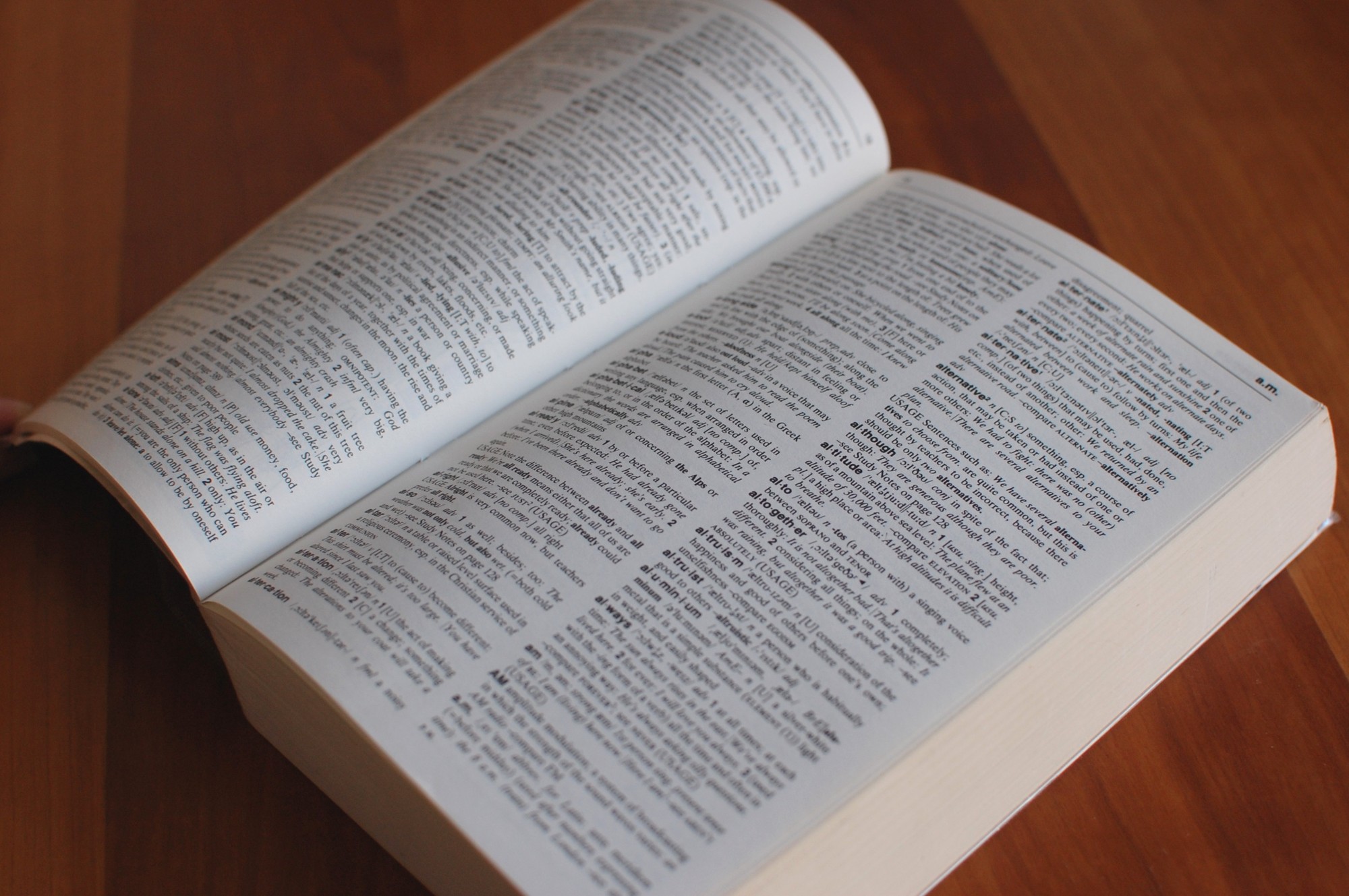
右綴じと左綴じの使い分け方は、本文が縦書きがメインなら「右綴じ」、本文が横書きがメインなら「左綴じ」が一般的です。
また右綴じか左綴じかは、主に本文の書き方が縦書きなのか横書きなのかに加えて、それによる視線の移動方向によって決まります。
たとえば、縦書きの場合、視線は右から左に動くことから、右綴じが自然です。一方で横書きの場合、視線は左から右に移動するため、左綴じが自然というわけです。
具体的に…
「右綴じ」・・・小説、漫画、詩集など
「左綴じ」・・・英語や理科の教科書、楽譜、論文集など
縦書き横書きが混在して構成されている原稿は、右綴じが適しているとされています。
たとえば、雑誌のような縦書きと横書きが混在している冊子や写真やイラスト、マンガも縦書きと横書きが混在していますね。
こうした縦横混在型の冊子を作成する場合には、メインとなる文章が縦書きなのかはたまた横書きなのかで綴じ方を決めましょう。
マンガは主に右綴じです。
日本人作家が描いたマンガは、たいていは右から左へと読み進めるコマ割りとなっています。そのため、縦書きがメインの冊子であれば右綴じとなります。
IT系のテキストのような、本文中に横文字(英単語)が多く登場する文章であれば、横書きの方が読みやすいため、左綴じが適しています。
写真集やイラスト集など文章がメインではないケースでは、右綴じ左綴じどちらでも構いませんが、一般的には左綴じが多い傾向にあります。
内容のボリュームをコントロールしづらい論文集制作の場合、縦書きも横書きも複数ページに渡ってしまうケースがあります。そうしたケースでは、最初に縦書きの原稿をまとめて、最後に横書きの原稿をまとめて、どちらからも読み進められる構成にしておきましょう。論文集だけでなく、テキストや資料集なども、そういった体裁になっているものがあります。どちらかに統一した方が編集が楽になりますが、たとえば縦書きの古文書などを頻繁に引用する論文では縦書きのままが読みやすいですね。また、英単語の多い論文は必然的に横書きになります。さらに、追悼集に関しても、それぞれの作者の意向を尊重することが大切です。
右綴じでも左綴じでもない、その他に「上綴じ(うえとじ)」という方法もあります。具体的には、カレンダーや伝票などに多く用いられる綴じ方で、「天綴じ」や「上開き」とも言われます。
縦に開く綴じ方で、ページを上に開いていく形式となっています。

右綴じ、左綴じで冊子を作成する際には、冊子のデータは、綴じ方向を意識して作成することが大切です。
綴じ方向によって、原稿のノド*部分に必要な余白(15mm~20mm)やページ番号であるノンブル*の配置が変わるため、注意が必要となります。
たとえば、右綴じの同人誌では本を開いて右側のページが奇数、左側のページが偶数となります。したがって、奇数ページにおいては原稿の左側部分、偶数ページにおいては原稿の右側部分に余白を設定する必要があります。なお、ノド部分の余白は全ページ統一した幅であらかじめ設定しておくと読みやすくなります。
また、右綴じの同人誌のノンブルは、冊子を開いた状態で右側のページが若い番号となります。ノンブルは、断裁の目安となる仕上がりの線よりも5mm以上内側に入れるのがポイントです。こうすることで正しい順序でページが並んでいることがわかります。
このように、冊子の綴じ方向によってデータのレイアウト調整が必要になることから、事前に右綴じにするか左綴じにするかを決めておきましょう。また、データの調整が難しいという場合には、余白などがあらかじめ設定されているテンプレートを活用するのもおすすめです。
*ノドに関する詳しい内容は「ノドとは?」をご覧ください。
*ノンブルに関する詳しい内容は「ノンブルとは?」をご覧ください。
右綴じ、左綴じの使い分け方のルールについて解説してきましたが、おわかりいただけましたでしょうか。
右綴じ、左綴じの使い分けは、本文が縦書きがメインなら「右綴じ」、本文が横書きがメインなら「左綴じ」が一般的です。
右綴じ、左綴じどちらの綴じ方にするかどうかで、冊子の読みやすさが大きく異なります。また、データ入稿の際、綴じる方向を間違えてしまうとデータの再入稿を求められることもあるため、注意が必要です。
冊子印刷で不安やご相談がございましたら、大倉印刷へお気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフ一同、こころよりお待ち申し上げております。
大倉印刷は、2024年には文京区で創業40年となりました。
培った実績と経験で、短納期案件や少部数から多部数をこなしてきた豊富な実績がございます。
お客様の様々なニーズに応えるワンストップ生産体制にて、印刷、製本加工、納品・発送までの一貫生産都内有数印刷機器の保有数です。
文京区に自社および自社工場を持つ利便性の良さをお客様のご要望に最大限活用させていただきたいと思っております。
“右綴じ、左綴じの使い分け方”のことはもちろん大倉印刷だからこそ、できる形をご案内いたします。どんなことでも、お気軽にご相談お問い合わせください。
#右綴じと左綴じの使い分け方 #右綴じと左綴じの使い分け方ルール #縦書き右綴じ横書き左綴じ #上綴じ天綴じ上開き #綴じ方向意識 #ノド #ノンブル #大倉印刷 #印刷 #製本加工 #文京区印刷製本 #印刷会社 #製本会社