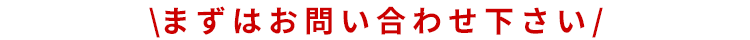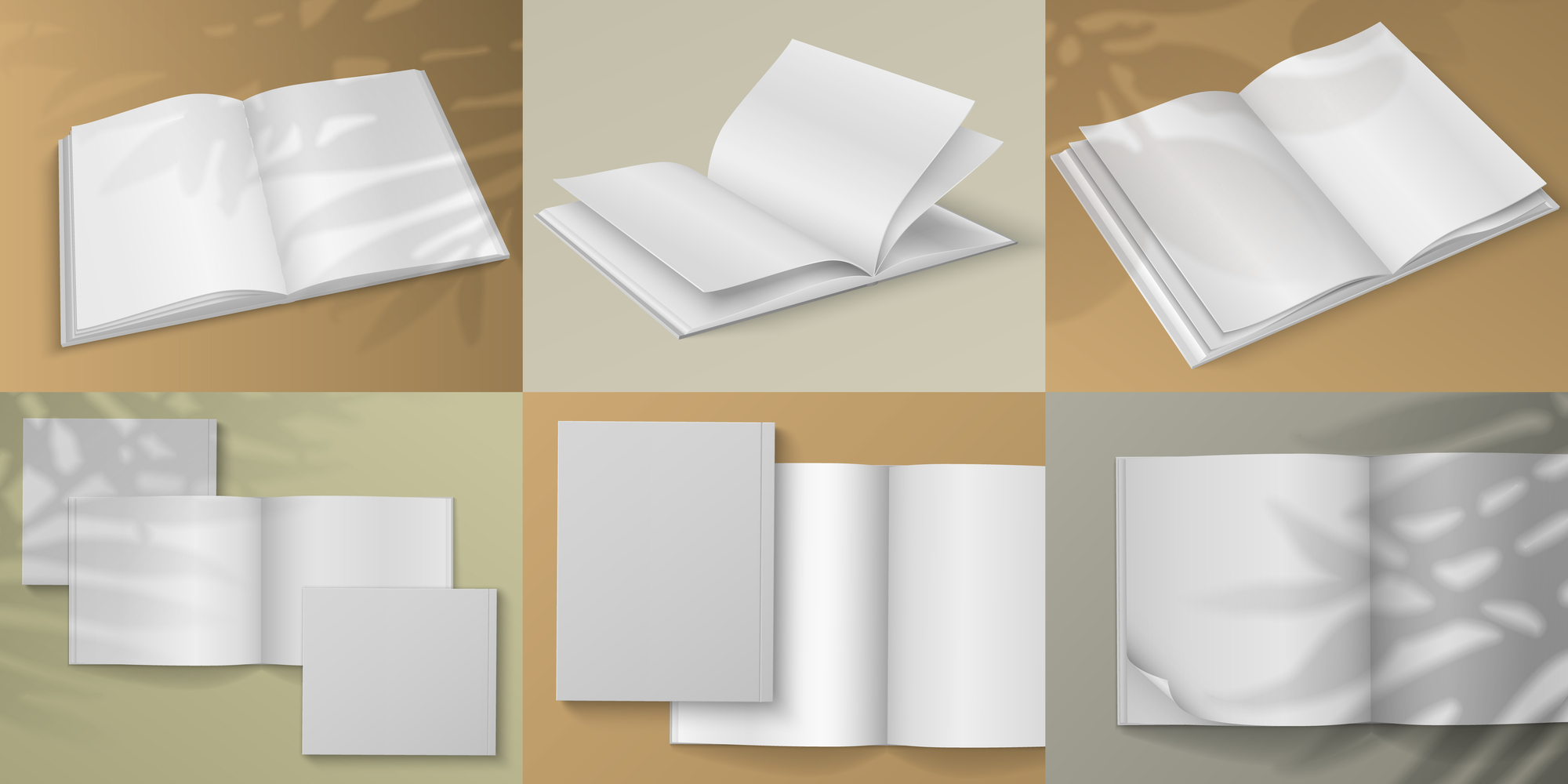
薄い冊子に向いている製本方法をご存知でしょうか。
薄い冊子には、「平綴じ」「中綴じ」「無線綴じ」のいずれかが向いています。
今回は、それぞれの製本方法の違いと選び方についてご紹介します。
薄い冊子に向いている製本方法は、「平綴じ」「中綴じ」「無線綴じ」ですが、その中でも薄い冊子には中綴じが最も適していると言えます。
次の章からそれぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

平綴じとは、紙の端をホチキスで綴じる製本です。説明会資料や会議資料などを作成する際に用いられ、最も簡易的な製本方法で誰でも簡単に作ることができます。平綴じは、紙の端から5mm程度のところをホチキスで1~3か所程度留めて製本されることから、ホチキス留めとも呼ばれます。平綴じは、その構造上綴じ側のノド*の部分のギリギリまでページを開いて見ることはできません。そのため、見開きデザインを重視している冊子には不向きと言えます。また、平綴じは、一般的には針金で留めますが、なかには糸で留めたり、綴じた後に背の部分に糊を塗布して表紙を貼り付けることもあります。
*ノド・・・本を開いたときに綴じられている内側のこと。
平綴じ製本で対応可能なページ数は、印刷会社によって異なりますが、大倉印刷では30枚までを綴じることが可能です。
ページを重ねて上から綴じるため、ページ数は2の倍数になっています。平綴じは、比較的ページ数が少ない冊子向けと言えます。というのも、ページが多すぎてしまうと、針金の長さが足りず、綴じることができません。もし綴じることができても、強度が弱くなってしまいます。
対応できる可能な最大ページ数は印刷会社によって異なるため、依頼する前に確認しておくようにしましょう。ページ数の多い冊子を作成する場合には、このあとご紹介します、無線綴じを選ぶことをおすすめします。
なお、大倉印刷の機械では、文京区最大の1度に30枚(紙の厚さ70㎏ベース)まで綴じることが可能です。31枚からは応相談となります。さまざまなサイズに対応が可能で、仕上がり(展開)サイズB6、B5、B4横(短辺側綴じ)、A5、A4、A3横(短辺側綴じ)となります。1日に2万冊の作成も承っております!(21枚から30枚までは1万冊)
平綴じ製本がよく用いられる冊子は、以下のとおりです。
平綴じは、簡易的な冊子や配布物が多い印象ですが、実は伝統的な和本、伝票などにも幅広く使用されている製本方法です。
平綴じの最大のメリットは、何と言ってもその手軽さです。
平綴じは、自分で作成することも、印刷会社へ依頼することもどちらもおこないやすいため、初めて冊子を作る場合でもおすすめの製本方法と言えます。
平綴じのデメリットは、見開きのレイアウトには適さないという点です。
こうしたことから、ページをまたぐ見開きの写真やイラストは避ける、余白を多めにとるなど、データ作成時に注意を払う必要があります。
先ほども触れましたが、平綴じのデータを作成する際は、「ノド側の余白」を意識しましょう。紙の端からホチキス留めした部分までのノド側は、冊子として製本すると隠れて見えなくなってしまいます。そのため、ノドから10mm~15mmの範囲には重要なイラストや文字を配置しないよう注意が必要です。
その一方で、背景のパターンや色に関しては、ノド側ギリギリまでレイアウトをしておいたほうが良いというケースもあります。というのも、こうしたレイアウトにすることで、印刷のズレが生じた場合でも、ページ内の絵柄が見切れてしまうということを防ぐことができるからです。

中綴じとは、印刷した用紙を重ねて中心から二つ折りにし、折った部分を針金や糸で綴じる製本方法です。平綴じと同様に、ホチキスで留める製本方法となりますが、冊子の折られている一で留めるため、平綴じとは異なり、ノド側いっぱいまでページを開くことが可能です。したがって、写真やイラストなど見開きでレイアウトした冊子にも適している製本方法と言えます。
また、中綴じは、見開きを重ねて綴じているため、ページ数は「4の倍数」となります。取扱説明書やパンフレット、カタログ、会社案内、企画書等、背表紙が無くページ数が少ない冊子によく使われます。
その一方で、平綴じ同様にホチキスの針の長さ分しか綴じることができないため、ページ数の多い冊子を作る際には、別の製本方法を選択する必要があります。
中綴じに関する詳しい内容は、「中綴じ製本とは?ページ数の少ない冊子におすすめの製本方法をご紹介します!」をご覧ください。

無線綴じとは、印刷された本文を表紙でくるみ、背表紙部分に接着糊を使用して冊子にする製本方法のことです。
無線綴じは、本文ページを重ねて糊を塗布するため、平綴じや中綴じとは異なり、ページ数が数百ページにものぼるような冊子でも対応が可能です。また、背表紙ができるのが特徴です。しっかりとした丈夫なつくりになるため、高級感のある冊子に仕上がります。一般的にページ数は「表紙4ページ+本文は8の倍数*」となります。ページ数の多いカタログや教科書、記念誌、小説などによく用いられる製本方法となっています。
*大倉印刷の機械なら、4ページの薄物の冊子も無線綴じが可能です!ぜひご相談くださいませ!
無線綴じの注意点として、内側のページになればなるほど綴じ部分が平らに開きづらくなってしまうということです。そのため、見開きのレイアウトにはあまり向いているとは言えません。そこで、ページの開きやすさが気になる場合には、「PUR製本」がおすすめです。PUR製本なら、ノドの部分までしっかりと開くことができるので、読みやすさやコピーのしやすさも格段にアップします。また、本を手で押さえていなくても開いた状態をキープできるため、レシピ本や楽譜などの製本に適しています。
無線綴じに関する詳しい内容は、「無線綴じとは?中綴じとどう違うの?メリット・デメリットについてもご紹介!」をご覧ください。
PUR製本に関する詳しい内容は、「PUR製本とは?無線綴じとの違いやメリットについてもご紹介!」をご覧ください。
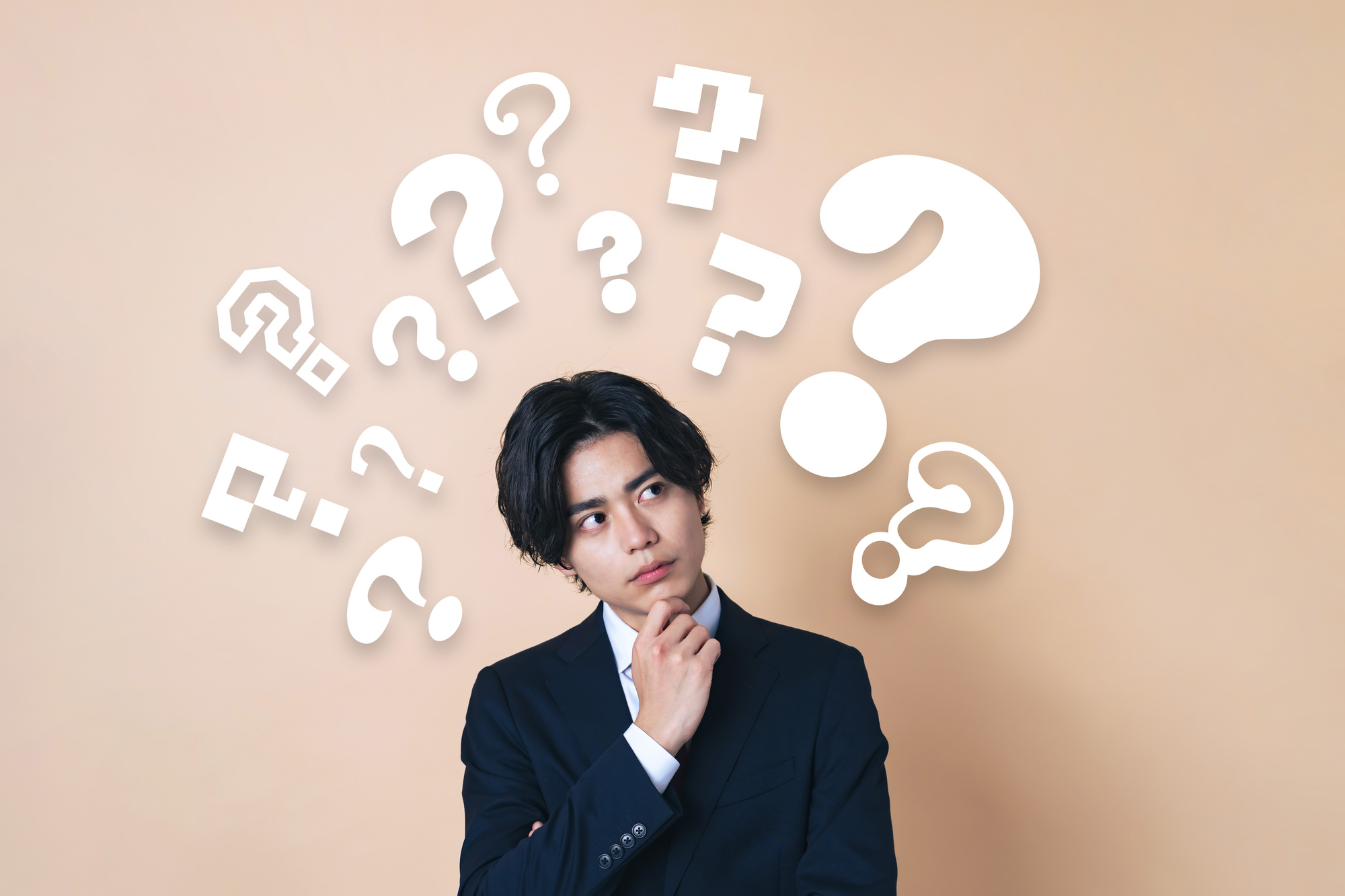
薄い冊子に向いている製本方法が、平綴じ・中綴じ・無線綴じということがお分かりいただけたかと思いますので、ここからはそれぞれの製本方法の使い分けについてご紹介します。
平綴じは、誰でも作成できる手軽な製本方法です。平綴じは、偶数ページであれば簡単に冊子にすることが可能です。両面印刷した原稿を重ねてホチキスで留めるだけで作成できます。
中綴じなら、ノドの部分までしっかりと開くことができるため、写真やイラストなどを見開きでレイアウトしたい場合におすすめです。平綴じと中綴じと、どちらにするか悩んだ場合には、写真やイラストが多めなら中綴じを選ぶようにしましょう。
ページ数の多い、厚めの冊子を作成したい場合には無線綴じを選ぶと良いでしょう。平綴じや中綴じではホチキス留めができる範囲に限りがありますが、無線綴じなら100ページ以上の冊子にも対応できます。
無線綴じでは背表紙ができ、背文字も入れることが可能です。平綴じや中綴じは背表紙ができません。平綴じに表紙をかぶせる方法もありますが、通常より工程が多くなってしまうため、コストが高くなります。したがって、背表紙のある冊子を作りたいという場合には、無線綴じを選んでおくと良いでしょう。
今回は、薄い冊子に向いている製本方法についてご紹介してきましたが、いかがでしょうか。
薄い冊子には、「平綴じ」「中綴じ」「無線綴じ」で製本する方法があります。それぞれの製本方法には特徴がありますので、どんな冊子を作成したいかで選択すると良いでしょう。
大倉印刷では、薄い冊子を作成するお手伝いをすることができます。「平綴じ」「中綴じ」「無線綴じ」どの製本方法が良いかお悩みの方は、ぜひ大倉印刷にご相談くださいませ!これまで培ってきた経験と技術で、皆様の大切な一冊を作るお手伝いをさていただきます。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
大倉印刷は、2024年には文京区で創業40年となりました。
培った実績と経験で、短納期案件や少部数から多部数をこなしてきた豊富な実績がございます。
お客様の様々なニーズに応えるワンストップ生産体制にて、印刷、製本加工、納品・発送までの一貫生産都内有数印刷機器の保有数です。
文京区に自社および自社工場を持つ利便性の良さをお客様のご要望に最大限活用させていただきたいと思っております。
“平綴じ・中綴じ・無線綴じでできる薄い冊子”のことはもちろん大倉印刷だからこそ、できる形をご案内いたします。どんなことでも、お気軽にご相談お問い合わせください。
#薄い冊子製本方法 #薄い冊子平綴じ #薄い冊子中綴じ #薄い冊子無線綴じ #PUR製本 #大倉印刷 #印刷 #製本加工 #文京区印刷製本 #印刷会社 #製本会社